物事にはすべからく「始まり」があります。
はじめに
頭髪をはじめとした毛は、外からの有害な刺激から身体を守り、体温の調節や、触覚などの知覚を担うなど大切な役割を持っています。美容業界ではときに「ムダ毛」などという心ない言葉が使われますが、本来「ムダな毛」などないのです。
大切な役割を担っているからこそ、抜けてしまった後も、新しく補充されます。そのために伸びては抜け、また新しく生えてくるという循環を繰り返します。
人間は大昔から、どの国に生まれても毛が伸びては抜けてを繰り返してきました。しかし、文明が誕生すると、ただ伸びるに任せておけなくなり、長くなった髪を「どうにしかしなければ!」と考えるようになったのです。
こうして人類の歴史に登場したのが、理容師、そして美容師なのです。
はじまり
髪を切って整える「理容」は、その存在が紀元前3500年ごろ、すなわち青銅器時代の遺物としてのカミソリの発見で確認できるそうです。
古代ギリシャや古代ローマでは、男性の髪を切る店があったと言われています。ちなみに女性は家の中で髪を切っていたようです。「古代」ですから、やはり文明の始まりから「理容」が登場していたようです。
また、ローション、ハサミ、スタイリング剤などを入れる美容師用のケースが古代エジプトの遺物として発見されています。
時代が下り、17世紀のヨーロッパではすでに、美容師はれっきとした職業として考えられていたそうです。
縄文時代
日本でも縄文時代の土偶に、さまざまな髪型ではないかと思われるデザインがあったそうです。そのため、やはり文明が誕生したころから、髪を伸ばしっぱなしにせず、整える工夫があったのではないかと考えられています。
ちなみに縄文時代とは、紀元前14000年ごろから紀元前10世紀ごろの時代を言います。この縄文時代の早期、具体的には今から7000年ほど前に作られたと思われる、木製のクシも見つかっているそうです。
髪結い
日本では昔から、伸びすぎた髪を切って整えるのではなく、結って整える「髪結い」が定着していました。
鎌倉時代には、髪の手入れを行う仕事が存在したそうです。鎌倉時代と言えば、12世紀末から1333年までです。
16世紀中期の室町時代には、京都でクシやハサミ、毛抜きを用いた「髪結床」が町中に存在していたそうです。「髪結床」の「床」が、「床屋」という名称の由来にもなっているようです。
この室町時代には月代が広まっています。月代は、まげ頭で、前頭部から頭頂部にかけての頭髪を剃りあげた部分のことです。月代を自分で剃ることは難しかったので、これが髪結いの仕事になっていたそうです。
髪結いは江戸時代には広く普及し、床屋は多くの男性が集まる社交場にもなっていたようです。また、髪を結うだけではなく、ヒゲを剃ったり、眉を整えたり、耳掃除を行うなど、施術内容は幅広く、修業を積まなければできない専門的な技術職でした。
一方、女性は、江戸時代の初めごろまでは自分で髪を結うことが「女性のたしなみ」と考えられていました。しかし、結い方が複雑化していき、髪結いに依頼するようになっていったようです。ただ、男性のように「髪結床」に行くのではなく、デリバリーで髪を結う「廻り髪結い」という職業が活躍したと言います。
断髪令
1868年、明治時代が始まると、明治政府は江戸時代までの習慣を捨て、日本人の生活を欧米化させようとしました。そして1871年、散髪脱刀令を公布したのです。
散髪脱刀令は通称を断髪令と言い、まげを結わずに髪型を自由にして構わないという布告でした。
こうして日本は「髪は切らずに結う」という文化から「髪を切って整える」文化に移行していったのです。同時に、それまでの髪結床は理髪店になっていきました。
美容学校の設立
明治時代の末には、男性の頭髪を散髪する職業を指す理髪師という呼称も一般化。理髪師は徒弟制度または年季奉公などでの見習いを経て道具をそろえ、約5年で開業するのが一般的だったようです。
大正時代(1912~1925年)から昭和にかけて、東京、大阪、愛知、京都などで美容学校が設立されていきました。理容師、美容師が、きちんとしたカリキュラムで理容・美容の技術を学ぶ職業となっていったのです。徒弟制度による職人的なイメージを刷新する狙いもあったようです。
理容師法の誕生
1947年、すなわち昭和22年に理容師法が公布されました。これによって理容、理容師が正式に定義づけされたわけです。
美容師法の誕生
1957年、すなわち昭和32年、美容師法が施行されました。これによって美容、美容師が正式に定義づけされたわけです。
今現在の美容師の歴史はここから始まったと言えます。
まとめ
人間は大昔から、どの国に生まれても毛が伸びては抜けてを繰り返してきました。そして文明が誕生すると、ただ伸びるに任せておけなくなり、長くなった髪を「どうにしかしなければ!」と考えるようになったのです。
日本では、紀元前14000年ごろから紀元前10世紀ごろの縄文時代には、長くなった髪を整えていたのかもしれない、という遺跡も見つかっています。
そこから考えると、現代の美容師はたかだか60数年の歴史しかないということです。逆に言うと、これからもまだまだいろいろ変化していく可能性があると言えます。もしかしたら進化するのかもしれません。楽しみです。
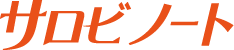



コメント